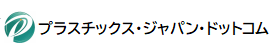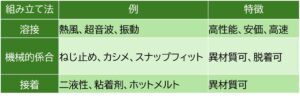アメリカ成形業界状況(2025.09) ―雑誌から垣間見る―
佐藤功
佐藤功技術士事務所
アメリカのプラスチック成形業界の最新動向を解説。K2025プレビューや環境対応技術、金型冷却・押出スクリュー冷却、一軸延伸フィルムなど最新技術の展望を紹介します。
1. 業界動向
7月の産業指数は48.4と50(好不況の分岐点)を前に4月以来足ふみが続いている。これを反映して原料樹脂価格も低位安定が定着しており、ほとんど動いていない。高関税で国内成形要請が増えているが、モルダーは現業のコストアップ対応に追われており、新しい仕事を取り込む余裕がない。関税問題の見通しの立たない状況が続く限り好況感は戻ってこないだろう。
2. K2025プレビュー
今号はK2025のプレビューの特集号になっており、かなりのページ数が割かれている。ここから技術動向を探ろうとしたがうまく行かなかった。言葉は違うが多くの出展者がテーマとして「環境対応と情報化」を掲げている。知りたいのは具体論だが「最新の制御によって」とか「原料を植物由来に」と言う程度に一般化されてしまっている。またブースの広さ、出展デモ機の台数や、デモ成形の内容などがにぎわしている。取り上げられている企業や製品もどのような基準で選定されたか分からない。
ある意図を持って、会場を回り、担当者から直接情報を得ることの重要性を痛感した。今後行われる見学の報告に期待したい。
日本でニーズがあるかどうかは分からないが、後述するインフレ一軸延伸技術は材料メーカー成形機マーカーがそろって展示するようだ。意識して各社の技術を比較すれば開発のねらい、技術の本質が理解できるかもしれない。材料、市場動向、延伸などの加工技術が絡んでいるので、他の分野でも参考になるはずだ。
3.技術解説
3-1 金型冷却
金型は冷却水で温度調整している。冷却水孔とキャビティ表面の距離、水孔間隔が指定される。冷却水量も乱流域になるよう設定される。所定量の冷媒が媒冷媒を細い管に流すためには高い圧力損失を伴う。水冷却回路の圧損計算が行われていないことが多く、配管径が細く、接続金具の圧損が大きく、しかもポンプの吐出圧が低いことが多い。このため、実際の金型ですべての水路で乱流になっていないケースが良くある。
3-2 押出スクリュー冷却
スクリュー冷却は喰い込み安定に有効だがあまり使われていない。スクリュー供給部の芯に数ピッチ分穴をあける。この穴にロータリージョイントを利用し細管を通し、穴奥まで水を注入する。細管から出た水は管の外側を通ってスクリューの根元側に戻る。流量調整を行うか金型温調機を使ってスクリュー供給部の温度を40~50℃程度に調整する。
3-3 重合と特性
プラスチックはモノマーを重合して作られる。重合法に縮合重合と付加重合がある。縮合重合は付加重合に比べ反応速度が遅く、低分子分が残る。分子鎖に極性基を持っているのも特徴だ。
例えばナイロンもABSも吸水する。ABSは側鎖のAN基が極性を持っているため吸水する。このまま成形すれば成形中に水分が気化してシルバーになる。ナイロンの場合はアミド結合が親水性だ。吸水したまま高温になるとアミド結合を加水分解し分子切断が起きる。重合形式からこのような成形挙動の違いを理解できるようになる。
3-4 一軸延伸インフレフィルム
一軸延伸フィルムは多孔性フィルムのような特殊な分野にしか使われなかったが、包装材の単一材料化の一環として剛性などの性能が注目され、活用が進んでいる。製膜機の後に設置されたローラーで加熱、延伸、アニール、冷却を行う。既存の製膜装置を改造することも出来るがスペースが確保できないことが多い。また、延伸するため、巻き取り速度が高くなり、巻き取り機の増速が必要な場合がある。
有力機械メーカーReifenhauser 、W&H、Hosokawa-alpineはいずれもK2025に出展し、それぞれの特徴をアピールする。 当然ながら対応した材料が必要で、Dow、Exxon、Shell、Nova、LG化学などが専用グレードをそろえている。
4.ケーススタディ
大口径パイプ成形
エジプトのPlastic Pipes & Productsは淡水装置用に最大直径3mのHDPEパイプを生産している。押出機は溝付きバレルとスタティックミキサーを備えており、樹脂温度の低温化に成功した。このためダイ出口のたわみが減り、寸法精度が大幅に向上し、ばらつきを規格の半分に抑えることが出来た。高精度化はユーザーから歓迎されただけでなく、目付の低減、使用電力につながりコスト低減に貢献した。
5. あとがき
酷暑が終わりそうにない。地球温暖化が原因だと言われている。これに関しては様々な努力をしてきたつもりだが阻止できていない。我々の努力は何だったのか、そしてどんな貢献をしたのか考えなければならない。